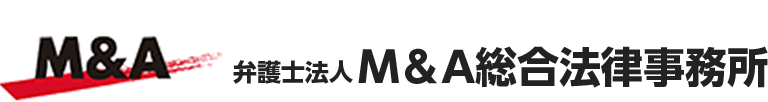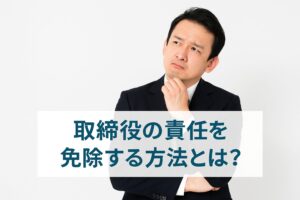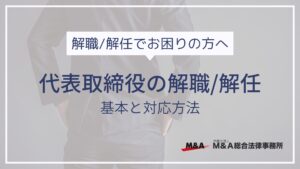取締役(役員)解任のリスクや手続き方法とは?役員が不当解任された際の対処方法も解説
お困りではありませんか?
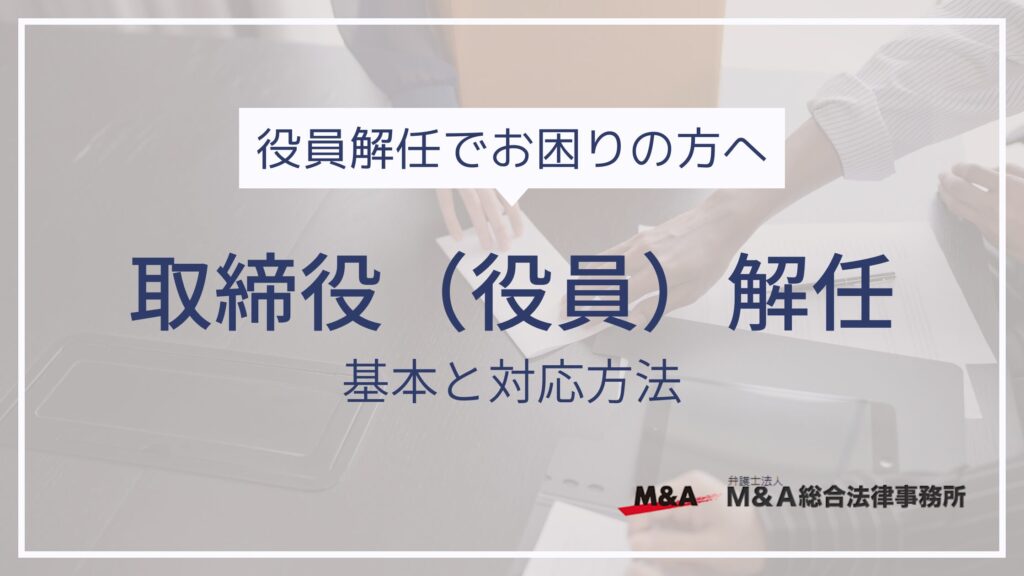
取締役や役員として会社に尽くしてきたのに、突然「解任」「辞任してほしい」と告げられた。
そんな場面に直面すると、多くの方がショックや不安で頭が真っ白になってしまいます。「本当にこんな扱いを受けなければならないのか」「退職慰労金(役員退職金)や今後のキャリアはどうなるのか」と悩まれる方も少なくありません。
本記事では、「役員解任」「取締役 解任」「役員 解任」をめぐる基本的な法律のルールから、正当な理由がある場合・不当解任になり得る場合の違い、損害賠償や退職慰労金のポイント、解任・解任されそうなときの具体的な対処法までを分かりやすく解説します。
取締役・役員解任とは?解任と退任・辞任の違い
「役員解任とはそもそも何か?」「退任や辞任との違いは何か?」。ご自身の状況が「解任」「退任」「辞任」のどれに当たるのかを確認していただくことが、この先の損害賠償や対処方法を検討するうえでの出発点になります。
取締役・役員の解任とは?
会社法上の「役員」とは、取締役・会計参与・監査役を指します。本記事では、読者の多くが想定する取締役を中心に、これらの役職をまとめて「役員」と呼びます。なお、執行役は指名委員会等設置会社における業務執行機関であり、いわゆる「執行役員」は就業規則上の社内役職にとどまることが多い点には注意が必要です。
「取締役解任」「役員解任」とは、本来の任期がまだ残っているにもかかわらず、株主総会の決議などにより、会社側の意思で任期途中に役員の地位を失わせることをいいます。
会社と役員との関係は、法律上は委任契約またはこれに類する関係です。そのため、役員解任は、会社側が一方的にその委任関係を打ち切る行為であり、会社の経営体制やガバナンスを維持するための重要な仕組みでもあります。経営方針が合わなくなった場合や、新たな経営体制に切り替えたい場合などに、役員の交代手段として用いられます。
他方で、解任される側の役員にとっては、役員としての地位の喪失、役員報酬や退職慰労金(役員退職金)への影響、今後のキャリアや評判への影響など、非常に大きな不利益が生じ得る出来事です。
法律上は、取締役は株主総会で「いつでも解任され得る立場」にありますが、任期途中の解任について正当な理由や適切な手続きが欠ける場合には、会社が損害賠償責任を負う可能性があります。
解任と退任の違い(任期満了退任との違い)
ここでは、似ているようで意味が異なる「退任」と「解任」の違いを紹介します。
退任とは、任期が満了したり、あらかじめ予定されていた理由によって役員の任期が終わり、その結果として役員でなくなることをいいます。
この場合は、もともと定められていた任期の終わりまで役員を務めることが前提ですので、役員側から見ると「予定どおり」任期を終えた形になります。
これに対して、解任は、任期の途中で会社側の判断により役員の地位を失わせるものです。
本来であれば、任期が終わるまで役員報酬を受け取ることが期待されているところ、会社側の事情などにより途中で役員から外されることになります。
そのため、解任が適切だったかどうかは、役員の生活・キャリアに直結する重大な問題になります。
中には、解任に近い状況でありながら、外向きには「任期満了による退任」と説明されるケースもあります。また、退任の前に任期を短く変更しておき、退任とする方法が取られることもあります。
このような場合には、
- 元々の任期はいつまでだったのか
- 任期が途中で変更されていないか
- 任期の変更や退任の流れに不自然な点がないか
といった点を確認し、「形式上は退任でも、実質的には解任といえないか」が問題となることがあります。
ご自身のケースを考える際には、元の任期、実際に役員でいられた期間、退任に至る経緯を時系列で整理してみることが、後の判断材料になります。
解任と辞任の違い
続いて、「辞任」と「解任」の違いを確認します。
会社から「辞任という形にしてほしい」と言われている場合には、とくに注意が必要です。
辞任とは、役員ご本人の意思で役員の地位を退くことをいいます。一般的には、役員本人が辞任届を提出し、会社がそれを受理する形が取られます。
これに対して、解任は会社側の意思決定によって役員の地位を失わせるものです。役員本人が納得しているかどうかにかかわらず、会社が「解任する」と判断し、必要な手続きがとられれば解任が行われます。
問題になりやすいのは、会社から「解任という形にはしたくないので、辞任にしてほしい」「円満退任ということにしておきましょう」と求められる場面です。
会社としてはトラブルを避けたい、社内外の印象を和らげたいという思いから、辞任や「円満退任」という言葉を使うことがあります。
しかし、実際には会社から強い要請や圧力があり、実質的には会社の判断で役員の地位を手放さざるを得ない状況であるにもかかわらず、形式上は「本人の辞任」と整理されてしまうと、後から「不当な役員解任にあたるのではないか」「残りの任期分の報酬について損害賠償を請求できるのではないか」と主張することが難しくなるおそれがあります。
また、形式上「辞任」で処理されると、周囲から「自ら辞めた」という印象を持たれやすい、会社側から「合意のうえで辞任した」と説明されるといったリスクもあります。
会社から辞任を強く求められたときには、
- なぜ辞任という形にしたいのか
- 今後の待遇(退職慰労金、持株の扱いなど)はどうなるのか
- どのような内容の書面にサインを求められているのか
をよく確認する必要があります。
納得できないまま、その場の雰囲気で辞任届や合意書に署名押印してしまうことは避けたほうが安全です。
取締役(役員)の解任は出来るのか?
会社法上、取締役を解任するかどうかは、原則として株主総会の普通決議によって決まります。株主が、会社の経営を任せている取締役の人選を、必要に応じて見直せるようにするためです。この意味で、取締役は「いつでも株主総会で解任され得る立場」にあります。
任期途中で解任が行われた場合には、「解任に「正当な理由」があったのか」「株主総会の開催や議案の内容など、解任に至る手続きが適切だったのか」といった点が問題になります。
一般的には、正当な理由のない任期途中の解任については、会社がその取締役に対して損害賠償責任を負う可能性があります。損害としては、
- 残りの任期の間に受け取れるはずだった役員報酬
- 条件によっては、退職慰労金(役員退職金)など
が検討対象になります。
また、形式上は「役員解任」という手続がとられていても、解任理由が抽象的で具体性に欠ける場合や株主総会の準備や説明が不十分で、手続きに大きな問題がある、といった事情がある場合には、取締役側から「不当な解任ではないか」として争われることがあります。
「役員 解任」が現実の問題として生じているときには、
- 法律上、取締役は株主総会で解任され得る立場にある
- ただし、解任理由や手続きに問題がある場合には、会社が損害賠償責任を負う可能性がある
という二点を前提に、ご自身の状況を整理していくことが重要です。
取締役(役員)解任の適切な手続き方法
ここからは、「役員の解任は法律上どのように位置づけられているのか」「会社はどのような手続きを踏むべきか」という全体像を紹介します。ここを押さえておくと、ご自身の解任が適切な流れで行われたのか、どこに問題があり得るのかを判断しやすくなります。
取締役(役員)解任の基本的な法律ルール
まずは、役員解任に関する法律上の大枠を確認します。「どの機関が」「どのような考え方で」解任を決めるのかを押さえておくことが重要です。
(1)株主総会による「いつでも解任できる」という原則
会社法上、取締役は株主総会の決議によっていつでも解任することができるとされています。これは、会社の経営を任せている取締役に問題が生じた場合や、経営方針を見直したい場合に、株主が人選を柔軟に変更できるようにするための仕組みです。
取締役の解任を決める株主総会の決議は、原則として 普通決議 によります。普通決議とは、定款に別段の定めがない限り、議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成で可決する形です。
したがって、「株主総会が開かれた」というだけでは足りず、出席状況や賛成票数の前提が整っていたかも重要になります。
(2)正当な理由と損害賠償の関係
任期途中の解任は、取締役側にとって大きな不利益となり得ます。そのため、会社法は「いつでも解任できる」という原則を認めつつも、正当な理由のない任期途中の解任については、会社が損害賠償責任を負う可能性があると定めています。
ここでいう「損害」としては、一般的に次のようなものが問題になります。
- 残りの任期の間に受け取れるはずであった役員報酬
- 退任時に支給されることが見込まれていた役員退職慰労金(役員退職金)の一部
つまり、「株主総会で解任すること自体」は法律上認められているものの、正当な理由がないのに任期途中で解任した場合には、その結果生じた損害を会社が金銭で補償しなければならないことがあるという構造になっています。
(3)任期の長さと解任リスクの関係
取締役の任期は、会社の種類や定款の定めによって異なります。公開会社では原則として2年、非公開会社では定款で定めることにより最長10年まで任期を伸ばすことができます。任期が長いほど、任期途中で解任した場合の損害賠償の金額も大きくなりやすくなります。
- 任期があと1年残っている取締役を解任する場合
- 任期があと5年残っている取締役を解任する場合
を比べると、後者の方が残りの任期分の役員報酬が多くなる分、損害額も大きくなりやすいと考えられます。
ご自身のケースを整理する際には、
- 元々の任期が何年であったのか?
- 解任が行われた時点で任期がどれくらい残っていたのか?
といった点を確認しておくことが、損害賠償の可能性を検討するうえでも有効です。
取締役(役員)の解任を決めるための社内手続き
次に、「会社の中でどのような流れで解任が決まるのか」という視点から整理します。
(1)まず確認したい会社の基本情報
役員解任の流れを考えるときは、最初に会社の基本的な仕組みを確認することが重要です。
例えば、
- 取締役会設置会社かどうか
- 代表取締役は取締役会で選定されているのか、株主総会で選任されているのか
- 定款で役員の任期や解任に関して特別な定めがあるか
といった点です。
とくに 取締役会設置会社 の場合、株主総会(臨時株主総会を含みます)を招集すること自体を 取締役会 で決めるのが通常です。取締役会の決定があいまいなまま株主総会が進んでいると、後から「適切な手続きだったのか」が争点になり得ます。
取締役会の決議は、定款に別段の定めがない限り、取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数の賛成で成立します。取締役会議事録は、解任の前提として「誰が」「いつ」「どの議題を」「どのように決めたか」を示す資料ですので、内容を確認しておくことが大切です。
これらによって、
- 取締役の解任を決める株主総会の準備を誰が行うのか
- 代表取締役の解職を決める取締役会をどのように開くのか
といった具体的な流れが変わってきます。
(2)役員解任が検討されるときの典型的な流れ
取締役の解任が議論されるとき、取締役会設置会社では、会社内部ではおおむね次のようなステップをたどることが多いです。
- 経営陣や主要株主の間で、解任の必要性について協議が始まる
- 解任理由や必要性を整理し、株主総会に付議するかどうかを取締役会などで判断する
- 株主総会の招集通知を発し、「当該取締役の解任」を議題として記載して株主に通知する
- 株主総会で解任の可否を決議し、株主総会議事録などに決議内容を記録として残す
- 解任が成立した場合、役員変更登記を申請する(原則として変更の日から2週間以内)
株主総会の招集通知は、会社の類型によって期限が異なります。公開会社では原則として 株主総会の日の2週間前まで に招集通知を発する必要があります。公開会社でない会社(いわゆる非公開会社)では 1週間前まで で足りますが、取締役会を置かない会社では定款でさらに短い期間を定めていることがあります。また、書面や電磁的方法による議決権行使を認める場合は、非公開会社でも2週間前までに招集通知を発する必要があります。
招集通知には、解任の対象となる取締役の氏名と、取締役の解任を決議することを 目的事項(議題) として明記します。招集通知に解任の議題がないのに当日になって突然解任が持ち出されるような進め方は、手続き面の問題として争われやすくなります。
また、解任によって取締役の人数が法令や定款の最低人数を下回ると、会社としての体制に支障が出ることがあります。取締役会設置会社は取締役が3名以上必要ですので、解任と同じ株主総会で後任取締役を選任するなど、欠員が生じない形になっているかも確認しておくとよいです。
解任が成立すると、取締役の氏名は登記事項として変更されます。会社は原則として 変更の日から2週間以内 に役員変更登記の申請を行う必要があり、登記が済むと登記事項証明書にも反映されます。
(3)誰が解任を「決めた」のかを意識する
ご自身が解任された、あるいは解任されそうな場合には、次のような点を意識して整理しておくとよいです。
- 解任の話を最初に切り出したのは誰か
- 実際に取締役の解任を決めたのは株主総会なのか、代表取締役の解職を決めたのは取締役会なのか
- その決定に至るまでの話し合いが、どのような会議体・どのような手順で行われたのか
これらは、後で「手続きに問題がなかったか」「誰を相手にどのような法的手段を検討すべきか」を考えるうえで、大切な情報になります。
取締役(役員)の解任にあたって準備しておくべきこと
役員解任が検討されている場面では、会社側にも役員側にも、多くの書類や記録が関係してきます。ここでは、とくにポイントとなりやすいものを整理します。
(1)会社側で用意されることが多いもの
会社側では、役員解任に向けて、次のような資料や記録が作られることがあります。
- 解任を検討する際の説明資料や社内メモ
- 解任理由や問題点をまとめた内部資料
- 会議での説明内容のレジュメやプレゼン資料
これらは、会社側が「なぜ解任する必要があると考えたのか」を示す材料になります。
(2)解任を決めたことを示す記録
解任を最終的に決めたときには、その内容が何らかの形で記録として残されるのが通常です。例えば、
- 会議の議事録
- 決定内容をまとめた文書
- 決定通知や社内告知文
などがあります。
こうした記録は、後から「どのような理由で、どのような手続きで解任が行われたのか」を確認するための重要な手がかりになります。
(3)役員本人に対する通知・説明の文書
会社が役員解任を行うとき、役員本人に対して何らかの形で通知や説明が行われることが多いです。例えば、
- 解任の理由や時期を記載した書面(解任通知書など)
- メールで送られてきた解任の連絡
- 「辞任を求める」趣旨の文書
といったものです。
こうした文書は、役員側から見ても非常に重要です。
「どのような理由が示されているのか」「どのような経緯で解任が伝えられたのか」が、後の判断材料になりますので、受け取った書類やメールは削除せず、必ず保管しておくことをおすすめします。
手続きの不備があるとどうなるか
最後に、「解任の手続きに問題があった場合に、どのようなことが起こり得るか」を確認します。役員として会社の対応に疑問を感じている方にとって、重要なポイントです。
(1)手続きの流れに大きな問題があるケース
例えば、次のような場合には、解任の手続きに大きな問題があると評価されることがあります。
- 本来必要とされる株主総会決議や取締役会決議を経ていない
- 招集通知や議題の記載と、実際に決められた内容が大きく異なる
- 形式的な議事録はあるものの、実際には十分な審議や説明が行われていない
こうした場合、解任の有効性そのものや、後に行う損害賠償請求の範囲に影響を与える可能性があります。とくに、株主総会での解任決議に重大な手続き上の瑕疵があるときには、その決議自体が争点となります。
(2)手続きの問題と決議の効力・損害賠償の関係
手続きに問題があるからといって、常に解任が無効になるとは限りません。ただし、手続きが極端に不適切であったり、役員にとって著しく不公平な形で進められていたりする場合には、
- 株主総会決議の取消しを求めることができる可能性
- 場合によっては、決議の不存在・無効を主張する余地
- 少なくとも損害賠償の額や責任の有無に有利な事情として考慮される可能性
などが出てきます。会社法上は、一定の要件のもとで株主総会決議の取消しや不存在・無効の確認を求める制度が用意されており、解任決議もその対象となり得ます。
(3)会社・役員の双方にとって「きちんとした手続き」が重要
適切な手続きを踏むことは、役員の権利を守るために重要であるだけでなく、会社にとっても、自らの決定を正当に説明するために欠かせません。
- 会社側にとっては、後からトラブルになったときに「正当な理由と適切な手続きに基づいて解任を行った」と説明しやすくなる
- 役員側にとっては、自分がどのようなプロセスで解任されたのかを確認し、不当な点があれば決議の効力や損害賠償の有無を争うための材料になる
という両面があります。
ご自身の解任について「納得できない」「おかしいのではないか」と感じている場合には、解任理由の内容だけでなく、「どのような株主総会・取締役会が開かれ、どのような手順で、どのように伝えられたか」という手続き面にも目を向けて整理しておくことが重要です。
正当な理由がある取締役(役員)解任/不当解任になり得るケース
この章では、「どのような場合に役員解任の正当な理由があるといえるのか」「逆に、不当解任と争われやすいのはどのようなケースか」を整理します。
正当な理由とされやすい典型的な役員解任理由(役員解任理由)
まずは、一般的に「正当な理由がある」と評価されやすい典型例から確認します。ここに挙げる事情に当てはまるからといって、必ず解任が有効になるわけではありませんが、裁判例や実務で会社側が正当な理由として主張しやすい代表的な類型です。
(1)法令違反・背任・横領などの不正行為
もっとも典型的なのが、役員による不正行為です。
例えば、
- 会社の資金や資産を私的に流用した
- 架空取引・粉飾決算など、財務に関する不正行為を主導した
- 独占禁止法や金融商品取引法など、重要な法令に違反する取引を推進した
といったケースです。
このような場合、会社は「会社に重大な損害を与えた」「会社の信用を著しく失墜させた」として、解任の正当な理由があると主張しやすくなります。
他方で、会社から不正行為を指摘されたとしても、指摘されている行為が事実として本当に存在するのか、事実関係に誤解や誇張が含まれていないか、同種の行為について他の役員との間で責任の分担がどうなっているかといった点を丁寧に検証することが重要です。
(2)著しい職務不適任・業務遂行能力の欠如
役員として求められる職務を十分に果たしていないと評価される場合も、正当な理由があるとされることがあります。
例えば、
- 極端に業務の遂行が遅く、重要案件の決裁や対応が滞っている
- 重大な判断ミスを繰り返し、その結果会社に多額の損失が生じている
- 取締役会への報告や情報共有義務を怠り続け、経営判断に支障が生じている
といったケースです。
このケースで重要になるのは、「一度のミスがあったかどうか」ではなく、問題点を指摘された後も改善が見られないこと、他の役員と比較しても、著しく不適切な状態が継続しているといった事情がどの程度存在するかです。単なる能力不足や評価の相違だけでは足りず、会社の経営に支障を生じさせる程度にまで達しているかどうかが争点になります。
(3)健康上の問題により職務の継続が難しいケース
役員本人の健康状態の悪化により、職務を継続することが難しくなる場合もあります。
例えば、
- 長期間の入院や療養が必要で、取締役会への出席や意思決定への関与がほとんどできない状態が続いている
- 判断能力や記憶力に継続的な障害が生じており、経営判断に重大な支障がある
といったケースです。
このような場合、会社としては本人の健康に配慮しながら、まずは職務軽減や一時的な代行などの選択肢を検討すべき場面もありますが、それでもなお会社の経営を適切に行うことが難しいと判断される場合には、役員構成の見直しとして解任が検討されることがあります。
不当解任と争われやすい取締役(役員)解任のケース
次に、「会社が解任の理由だと主張しているものの、そのままでは正当な理由があるとはいえないのではないか」と争われやすいケースを見ていきます。
ここに当てはまる場合は、不当解任かどうかを検討する余地があると考えられます。
(1)経営方針の違い・人間関係の悪化のみを理由とする解任
よくあるパターンの一つが、「経営方針の違い」や「人間関係の悪化」を理由とする解任です。
例えば、
- 社長や他の役員と考え方が合わない
- 議論の場で対立することが多く、「扱いづらい」と見られている
- 新しい経営体制への移行にともない、特定の役員だけを外したい
といった事情が背景にあるケースです。
経営方針の違いや人間関係の問題そのものは、会社の運営に影響を与えることがありますが、だからといって直ちに「正当な理由がある」とはいえない場合があります。
会社側が表向きには「経営方針の違い」と説明しつつ、実際には特定の株主の意向を通すためや、内部の権力争いの結果として排除したいだけといった事情があるとすれば、不当解任かどうかを慎重に検討する必要があります。
(2)一時的な業績悪化を一方的に責任追及する解任
業績が悪化したことを理由に、特定の役員だけを解任しようとするケースもあります。しかし、業績悪化はさまざまな要因が絡み合って生じるものであり、ただちに一人の役員だけの責任といえるとは限りません。
次のような点を確認することが重要です。
- 業績悪化の主な原因は何なのか
- その役員だけに責任を負わせるのが公平といえるのか
- 他の役員にも同程度の責任があるのではないか
これらを無視して「業績が悪いから」「株主からの印象が悪くなるから」という理由だけで解任する場合には、正当な理由があるとはいえない可能性があります。
(3)説明があいまいなまま進められる解任
会社からの説明が、「総合的に判断した結果です」「信頼関係が失われたと判断しました」といった非常に抽象的なものにとどまり、具体的な事実や出来事が示されないまま解任が進められることもあります。
解任の理由があいまいなまま話が進んでいる場合は、その時点で一度立ち止まり、具体的にどのような行為や結果が問題とされているのか、それはいつ、どのような形で起きたのかを書面やメールで説明してもらうことが重要です。
任期短縮や役職変更を利用した「実質的な解任」
最後に、形式上は解任ではないものの、実質的には解任とほとんど変わらないケースについて整理します。表向きの説明と、役員が受ける不利益の大きさとの間にギャップが生じやすい場面です。
(1)定款変更による任期短縮を利用した退任
もともと任期が数年あった取締役について、途中で定款変更を行い、取締役の任期を大幅に短縮する。短縮後の任期満了を理由に「任期満了退任」として処理する。という方法がとられる場合があります。
定款変更自体は株主総会の特別決議により認められる手続ですが、その結果として特定の取締役だけが予定より大幅に早く退任させられているようなときには、なぜそのタイミングで任期を短縮したのかや、任期短縮の必要性が客観的に説明できるのかといった点を慎重に確認する必要があります。
事情によっては、任期途中の解任と実質的に同視できるとして、任期途中解任の場合と同様に損害賠償を求める余地が検討されることもあります。
(2)代表権や権限を奪うことで事実上のクビにするケース
形式上は取締役の地位が残っていても、
- 代表取締役の地位だけを解職して代表権を外す
- 業務上の権限や役割をほとんど与えない
- 重要な会議から外す、情報を共有しない
といった形で、実質的に会社経営への影響力を完全に排除される場合があります。
(3)形式は辞任・退任、実質は解任というケース
会社から「辞任という形にしてほしい」「円満退任としたい」と強く求められ、やむを得ず辞任届を提出したものの、実際には会社から強い圧力や説得があったケースや辞任以外の選択肢が事実上提示されていなかったという場合には、形式上は辞任・退任であっても、実質的には解任と同じではないかという問題が生じます。
このようなケースでは、
- 辞任を求められた具体的な経緯(会話内容やメールのやり取り)
- 辞任に応じなかった場合にどのような扱いになると言われていたのか
- 辞任を選ばざるを得なかった事情
をできるかぎり資料やメモで整理したうえで、不当な役員解任に当たらないかを検討していくことが重要です。
取締役(役員)を解任された場合の損害賠償・退職慰労金のポイント
ここでは、取締役や役員が解任された場合に「お金の面」「今後の生活やキャリアの面」でどのような影響が出るのかを紹介します。
とくに、正当な理由のない役員解任と損害賠償、退職慰労金の扱い、役員兼従業員の方の注意点を中心に説明します。
正当な理由のない役員解任と損害賠償請求
役員解任には、正当な理由がある場合と、そうとはいえない場合があります。ここでは、とくに正当な理由がない任期途中の役員解任と損害賠償の関係について整理します。
(1)正当な理由がない解任と損害賠償の基本的な考え方
会社法上、取締役は株主総会の決議によりいつでも解任することができますが、任期途中で正当な理由なく解任された場合には、会社がその取締役に対して損害賠償責任を負う可能性があります。ここでいう損害とは、簡単にいえば「本来の任期満了まで取締役として在任していれば得られたはずの利益が失われた部分」です。
典型的には、次のような項目が検討されます。
- 残りの任期の間に受け取れるはずであった月額の役員報酬の合計額
- 退任時に支給されることが見込まれていた役員退職慰労金(役員退職金)の一部
いくらまでが損害として認められるかは、会社との契約内容、これまでの支給実績、解任に至る経緯などによって変わります。実際にどの程度の金額を請求し得るかは、個別の事情を前提とした検討が必要です。
(2)損害として問題になることが多い項目
損害として主張されることが多いのは、次のような項目です。
- 月額の役員報酬 × 解任時点で残っていた任期の月数
- 一定の条件を満たした場合に支給されることが予定されていた退職慰労金のうち、支給される蓋然性が高かった部分
- ストックオプションや業績連動報酬など、解任されなければ相当程度の見込みで受け取れたと考えられる報酬
ただし、将来の報酬や退職慰労金については、「必ず支払われた」とまではいえない性質もあります。そのため、どこまでを損害として評価できるかについては、支給の条件、会社の業績、過去の運用実績などを踏まえた慎重な判断が必要になります。
(3)損害賠償請求を検討する際のポイント
損害賠償請求を検討する際には、次のような点を整理しておくと見通しを立てやすくなります。
- 元々の任期と、解任された時点での残りの期間
- 月額の役員報酬や賞与、業績連動報酬の決め方
- 退職慰労金などが定款・株主総会決議・社内規程でどのように定められているか
- 解任理由や手続きに、正当な理由の有無や手続き上の問題がないかどうか
取締役を解任されたら経済的にどのような影響が出るのかを考えるときには、感情的な納得感だけでなく、具体的な項目を一つずつ確認し、どの範囲まで損害として主張できる可能性があるのかを整理していくことが重要です。
役員解任で退職慰労金(役員退職金)はもらえない?
ここでは、役員の退職慰労金(役員退職金)がどのような仕組みで決められるのか、減額や不支給が問題になる典型的な場面を整理します。
(1)役員退職慰労金の基本的な位置づけ
役員の退職慰労金は、会社法上は「報酬等」に含まれるものと整理され、原則として定款または株主総会決議によって支給の有無や枠組みが決められます。株主総会で「退職慰労金は取締役会に一任する」といった決議を行い、その範囲内で具体的な金額を取締役会が決定する運用も見られます。
金額を検討する際には、在任期間、役職の重さ、会社への貢献度、会社の業績などが総合的に考慮されます。
そのため、退職慰労金が支給されるかどうか、いくら支給されるかは、
- 定款や株主総会決議・取締役会決議の内容
- 会社の退職慰労金規程や過去の支給実績
- 退任・解任に至った事情
といった要素を踏まえて判断されます。「解任だから必ずゼロになる」というものではありません。
(2)不祥事や重い責任を理由とする減額・不支給
役員解任の理由が、不祥事や重大な義務違反に関するものである場合、会社が退職慰労金の減額や不支給を主張してくることがあります。例えば、「横領や背任などの不正行為があったとされている」「重大なコンプライアンス違反に関与したとされている」といったケースです。
会社が「不祥事だから全額不支給とする」と一方的に決めれば常に許されるわけではありません。不正行為等が客観的事実として存在するのか、その行為の内容や結果が退職慰労金を減額・不支給とするほどのものか、減額の程度が過度ではないかといった点が問題になります。
事案によっては、一部減額にとどまるべき場合や、不支給までは認められないと評価される場合もあります。
役員兼従業員の場合の注意点(解任と解雇の違い)
取締役などの役員であると同時に、従業員としての立場も持っている方も少なくありません。いわゆる「使用人兼務役員」の場合、役員としての解任と、従業員としての解雇は別々の法律関係として整理する必要があります。
(1)役員としての地位と従業員としての身分は別
役員としての地位は、会社法上の機関としての地位に基づくものです。他方、従業員としての身分は、労働契約に基づく「労働者」としての地位です。
そのため、
- 取締役としては株主総会の決議により解任されたが、従業員としての雇用は継続している
- 取締役の解任と同時に、従業員としても解雇された
といった複数のパターンがあり得ます。役員解任の話が出たときには、問題となっているのは役員としての立場だけなのか?従業員としての雇用契約も終了させる意図があるのか?を明確に確認しておくことが重要です。
(2)従業員としての解雇には労働法上の制限がある
従業員としての解雇には、労働基準法や労働契約法など、労働者保護の観点から厳しい制限があります。特に、労働契約法16条は、解雇について「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合には無効」と定めています。
そのため、取締役としての解任が会社法上は有効と評価される場合でも、同時に行われた従業員としての解雇が有効と認められるとは限りません。役員解任と同時に解雇を告げられた場合には、役員の問題と従業員の問題を切り分けて、それぞれの法律に従って検討することが必要です。
(3)役員兼従業員の方が整理しておきたいポイント
役員兼従業員の方は、今後の選択肢を検討するために、次のような点を整理しておくとよいです。
- 役員としての報酬と、従業員としての給与がどのような根拠で決められていたか
- 役員としての地位が終了した後も、従業員として働き続ける選択肢があるのか
- 従業員としての解雇理由が、労働契約法16条などの要件を満たすといえるのか
役員解任と従業員の解雇が同時に進められると、状況は複雑になりやすくなります。早い段階で、役員としての立場と従業員としての立場を分けて整理し、必要に応じて専門家に相談することが望ましい場面も多くあります。
不当な取締役・役員解任かどうかを判断するチェックリスト
この章では、「自分のケースは不当な役員解任にあたるのか」を検討する際に、どのような点を確認すべきかをチェックリストの形で整理します。
解任の理由だけでなく、「どのような経緯で」「どのような手続きで」進んだのかも含めて見ていくことが大切です。
手続き面のチェック(解任決定のプロセス)
まずは、解任がどのような流れで決められたのかという「手続き面」を確認します。
理由の是非だけでなく、プロセスに大きな問題がないかどうかも、不当解任かどうかを判断するうえで重要な材料になります。
(1)どのような場で、誰が解任を決めたのか
次のような点を一つずつ振り返ってみてください。
- 解任の話を最初に切り出したのは誰か
- どのような場(会議・面談・メールなど)で解任の話が出たのか
- 最終的に解任を決めたのは誰(どの立場・どの機関)か
「気づいたらもう決まっていた」「誰が本当に決めたのかよく分からない」という場合には、手続き面に問題が潜んでいる可能性があります。
(2)説明や話し合いの機会があったか
解任に至るまでに、次のような機会があったかどうかも確認してみましょう。
- 事前に問題点を指摘され、説明を求められたか
- 自分の考えや弁明を伝える場があったか
- 意見の違いについて、冷静な話し合いの場が設けられたか
もし、いきなり「もう辞任してほしい」「解任することにした」と告げられたり、詳しい理由の説明もないまま、一方的に書類への署名を求められたというような場合には、手続きがあまりにも一方的である可能性があります。
(3)決定の内容が記録として残っているか
解任の決定は、通常、何らかの形で記録に残されます。
次のようなものがあるかどうかを確認してみてください。
- 会議の議事録やメモ
- 解任を知らせる通知文書やメール
- 社内向けの説明資料
もし「口頭でしか聞いていない」「書面は一切もらっていない」という場合には、後から事実関係を確認することが難しくなります。
可能であれば、解任の日時や内容が分かる記録(メールの履歴やメモなど)を、ご自身でも残しておくことが大切です。
(4)株主総会・取締役会の「形式」が整っているか
「解任が決まった」と言われていても、株主総会や取締役会の形式が整っていないと、決議の効力が争点になることがあります。次の点を一つずつ確認してみてください。
- 株主総会の招集通知は届いていたか、通知日と開催日の間隔は十分か
- 招集通知の議題に「取締役の解任」が明記されていたか
- 株主総会で 普通決議 の前提(出席状況と賛成票数)が整っていたか
- 取締役会設置会社の場合、株主総会の招集を取締役会で決めているか、取締役会議事録が残っているか
- 解任後に登記がされているか(登記事項証明書で確認できます)
これらの点があいまいなまま進んでいる場合は、解任理由とは別に、手続き面に問題が潜んでいる可能性があります。
解任理由のチェック(役員解任理由の妥当性)
次に、会社が主張している解任理由の内容を確認します。
「納得できない」という感情だけでなく、理由自体が法律上の「正当な理由」といえるかどうかの観点から整理することが大切です。
(1)解任理由は具体的に示されているか
まずは、解任理由がどの程度具体的に説明されているかを確認します。
- いつ、どのような行為が問題だったのか
- どのような結果や損害が生じたとされているのか
- 誰が、どのような点を問題視しているのか
がはっきりしているでしょうか。
「総合的な判断です」「信頼関係が失われました」といった抽象的な表現だけでは、正当な理由があるのかどうかを判断することは困難です。
(2)過去に注意・指導・改善要求があったか
何か問題があると言われているのであれば、その前に次のような対応があったかどうかも重要です。
- 問題点について、具体的な注意や指導を受けていたか
- 改善や再発防止を求められ、それに対応する機会が与えられていたか
- 他の役員に対しても同じような基準が適用されているか
もし、これまで特に注意や警告を受けたことがなかったのに、いきなり「重大な問題」として解任まで進んでいるのであれば、その妥当性を慎重に検討する必要があります。
(3)他の役員との比較で著しく不公平ではないか
また、同じような行動や判断をしている他の役員がいるのに、自分だけが解任の対象とされていないでしょうか。
- 同様のミスや評価の役員が複数いるのに、特定の一人だけが解任されている
- 特定の株主や経営者との関係性だけを理由に、排除の対象になっている
といった事情がある場合は、公平性を欠く扱いといえる可能性があります。
こうした点も、不当解任かどうかを検討するうえで重要な材料になります。
証拠として残しておくべき書類・データ
不当解任の可能性を検討し、必要に応じて会社と話し合いや交渉を行うためには、「証拠」となる資料をきちんと残しておくことが非常に重要です。
ここでは、特に押さえておきたいものを整理します。
(1)会社から受け取った書類・メール
まずは、会社から受け取った書類やメールを整理して保管しておきましょう。
- 解任を知らせる通知や案内文
- 辞任や合意退任を促す文書
- 解任理由や問題点を説明した資料やメール
これらは、会社がどのような理由で、どのような説明をしてきたのかを示す重要な証拠です。
紙ベースの書類だけでなく、メールやチャットツールのメッセージも、可能な範囲で保存しておくことをおすすめします。
(2)会議や話し合いの内容が分かる資料
解任について議論された会議や面談があった場合、その内容を示す資料も大切です。
- 会議の議事録
- 会議の配布資料やスライド
- 面談でのメモ(自分で取ったものでも構いません)
議事録などが会社側から共有されない場合でも、自分用のメモとして、
- 日時
- 出席者
- どのような話が出たか
- どのような発言や合意があったか
を簡単に記録しておくだけでも、後で思い出す際に大きな助けになります。
(3)日頃の業務や評価に関する資料
解任理由が「業務上の問題」や「能力不足」であるとされている場合には、日頃の業務や評価に関する資料も重要な証拠になります。
- 業績報告書や営業成績の資料
- 人事評価シートや面談記録
- 他の役員や社員からのメール(感謝や評価のメッセージなど)
これらは、「本当に業務上の問題があったのか」「会社の主張と実際の評価が食い違っていないか」を検討するうえで役に立ちます。
解任決議を争うための法的な手段の全体像
解任の理由や手続きに大きな疑問がある場合には、「おかしい」と感じるだけでなく、必要に応じて法的な手段を検討することも選択肢となります。ここでは、代表的な枠組みを整理します。
まず、取締役の解任は通常、株主総会の決議によって行われます。この株主総会の解任決議そのものに手続き上の問題がある場合には、会社法上、次のような訴えを通じて決議の有効性を争うことが検討されます。
- 株主総会決議の内容に取消事由があるときに、その取消しを求める訴え
- 招集手続や議事運営に重大な瑕疵があるなど、決議がそもそも存在しない・無効といえる場合に、その不存在または無効の確認を求める訴え
これらはいずれも、会社法に定められた手続に従って提起する必要があります。特に、決議取消しの訴えには原則として短い出訴期間が定められているため、「後からゆっくり考えればよい」と放置していると、争う機会自体を失ってしまうおそれがあります。
また、解任決議そのものを争わない場合でも、正当な理由のない任期途中の解任として損害賠償を請求するというアプローチもあります。この場合は、決議の効力そのものではなく、「解任の理由・経緯・手続き」と「生じた損害」との関係を中心に検討していくことになります。
どの手段を選ぶべきかは、
- 手続き上の問題が中心なのか、理由の内容が中心なのか
- 決議からどれくらい時間が経っているのか
- 経済的に回復したい損失が何か
といった事情によって変わります。違和感を覚えた段階で、できるだけ早い時期に、自分のケースがどの枠組みに当てはまり得るのかを専門家と一緒に確認しておくことが重要です。
小さな違和感もメモしておくことが大切
不当解任かどうかを検討するうえでは、「法律的におかしいかどうか」だけでなく、当事者として感じた違和感も大事なヒントになります。
- なぜこのタイミングだったのか
- なぜ自分だけが対象になっているのか
- なぜ具体的な説明を避けるのか
といった疑問があれば、その内容を簡単にメモしておくだけでも、後から状況を整理しやすくなります。
「なんとなくおかしい気がする」と感じたときこそ、
感情的に反応する前に、事実関係と証拠を一つずつ整理することが、不当解任への対応の第一歩になります。
不当に解任された・解任されそうな取締役(役員)の対処法
この章では、「すでに解任されてしまった方」「これから解任されそうだと感じている方」が、どのような順番で何をすべきかを、できるだけ具体的に整理します。
感情的に動いてしまうと不利になる場合も多いため、「まず何から手をつけるか」をイメージしながら読んでみてください。
解任を示唆された段階で行うべき初動対応
まだ正式な解任までは至っていないものの、上司や社長、他の役員から「辞任してほしい」「役員から外れることを考えてほしい」といった話が出始めた段階で、取っておきたい対応があります。
(1)口頭だけで終わらせず、書面・メールで内容を残す
最初の段階では、次のように口頭で切り出されることが多いです。
- 「そろそろ身の振り方を考えてほしい」
- 「このままだと解任も検討せざるを得ない」
- 「円満に辞任してくれると助かる」
このような話を聞いたとき、多くの方は驚きやショックで冷静に対応しにくくなりますが、ここで大切なのは、やり取りを記録に残すことです。
(2)その場で即答・即サインをしない
突然「辞任してほしい」と言われると、場の空気に押されて、「分かりました」とその場で答えてしまうことや辞任届や合意書にそのまま署名してしまうということも少なくありません。
しかし、一度辞任届や合意書にサインしてしまうと、後から「やっぱり撤回したい」と主張することは非常に難しくなります。
そのため、どれだけ強く求められても、「すぐには決められないので、持ち帰って検討したいです」と伝え、その場での即答・即サインは避けることをおすすめします。
(3)感情的な反応を控え、記録と情報収集に集中する
理不尽なと感じる場面では、怒りや悔しさから相手に強く反論したくなるかもしれません。しかし、その場で感情的にぶつかってしまうと、不利な発言をしてしまい、後から問題になったり、「協調性がない」「話し合いができない」といった印象を与えてしまうといったリスクがあります。
「納得はできないが、いったん今日は持ち帰って整理します」といった姿勢で切り上げ、その後、落ち着いて事実関係や書類の内容を確認していくほうが、有利な対応につながりやすくなります。
解任決定がなされた直後にやるべきこと
すでに解任が決定した、あるいは決定が伝えられた段階では、「事実の整理」と「選択肢の把握」が重要になります。
(1)いつ、どのような内容で解任が決まったのか整理する
まずは、次のような点を整理してみてください。
- 解任が決まった日(または通知を受けた日)はいつか
- 誰から、どのような形(対面・メール・書面など)で伝えられたか
- そのときに説明された解任理由は何だったか
可能であれば、その場でメモを取り、後から自分宛てにメールでまとめておくと、事実関係を忘れにくくなります。
(2)決定の根拠となる書類やメールを収集・保管する
次に、解任の決定や理由に関係しそうな書類やメールを集めておきます。
- 解任通知書や案内文
- 解任に関する社内メール
- 会議資料や議事録のコピー
こうした資料は、後から不当解任かどうかを検討するうえでの重要な証拠になります。
紙の書類だけでなく、メールのスクリーンショットやフォルダ分けなども有効です。
(3)取り得る選択肢を大まかに把握する
解任が決定したとき、多くの方が
- 会社に残るべきか
- 和解・合意を目指すべきか
- 損害賠償などの法的手続きも検討するべきか
といった点で悩まれます。
すぐに結論を出す必要はありませんが、
- 不当解任の可能性があるのか
- 損害賠償請求が現実的に見込めるのか
- 会社との関係をどの程度維持したいのか
といった点を、早い段階で専門家と一緒に整理しておくことで、後になって「もっと早く動いておけばよかった」と後悔するリスクを減らすことができます。
いつ弁護士に相談すべきか
最後に、「どのタイミングで弁護士へ相談したほうがよいか」という点について整理します。
結論からいうと、「少しでもおかしいと感じた時点」で相談していただくことをおすすめします。
(1)解任を匂わされた段階で相談するメリット
まだ正式な話にはなっていなくても、
- 「そろそろ身の振り方を考えてほしい」と言われた
- 「取締役会であなたの進退が議題になるかもしれない」と示唆された
といった段階で相談いただくと、次のようなメリットがあります。
- どのような発言・対応は避けるべきか、事前にアドバイスを受けられる
- どの書類・メールを残しておくべきかが分かる
- 将来の交渉に備えた「土台づくり」を、早い段階から進められる
初動を誤らないことが、その後の有利・不利を大きく左右することがあります。
(2)解任直後・交渉前に相談するメリット
すでに解任が決まった、あるいは決定を知らされた段階でも、交渉に入る前に一度相談しておくことをおすすめします。
- 解任の理由や手続きに問題があるかどうか
- 損害賠償や退職慰労金(役員退職金)についてどの程度主張できそうか
- 会社との交渉で、どこまで譲歩する余地があるのか
といった点について、第三者の目で整理してもらうことができます。
自分だけで交渉を進めてしまうと、「その場で言われるままの条件で合意してしまったが、後から考えると不利な内容だった」と後悔するケースも少なくありません。
(3)時間がたつことによる不利を避ける
時間がたつほど、関係者の記憶が薄れていく・メールや資料が廃棄される・会社との力関係が固定化してしまうといったデメリットが生じやすくなります。
「もう少し様子を見てから」と考えているうちに、取り得たはずの選択肢や証拠が失われてしまうこともありますので、少なくとも一度は早い段階で相談し、現時点での選択肢を把握しておくことが重要です。
会社側が取締役(役員)解任を行う際のリスクと予防策
この章では、会社側が役員解任を行う際にどのようなリスクがあるのか、それを避けるためにどのような点に注意すべきかを整理します。結果的として、会社側が適切な手続きを取ることは、役員側から見ても「不当な扱いを受けにくい環境」をつくることにつながります。
手続きの不備による解任無効・損害賠償リスク
会社側が役員解任を進める際、もっとも注意すべきポイントの一つが「手続きの不備」です。
解任の理由がどれだけ正当だと考えていたとしても、手続きに大きな問題があると、トラブルにつながるおそれがあります。
(1)解任の決定プロセスがあいまいな場合のリスク
解任が、
- 誰の権限で
- どのような手順で
- どのような場で
決まったのかがはっきりしていない場合、後から「有効な解任だったのか」が争われやすくなります。
例えば、
- 役員の一部だけで話し合い、正式な決定の場を経ないまま解任を伝えた
- 書面での記録をほとんど残していない
- 会議は開いたが、議事録の内容が不十分である
といったケースでは、「本当に会社としての意思決定があったのか」「手続きが適切だったのか」が問題になりやすくなります。
(2)手続きの不備が損害賠償額に影響する可能性
手続きの不備は、解任そのものの有効性だけでなく、損害賠償の範囲にも影響を与えることがあります。
- 解任の理由や経緯の説明が不十分であった
- 話し合いの機会を与えず、一方的に解任を伝えた
- あまりに短期間で解任を決めてしまった
といった事情があると、裁判などになった際に、会社側に不利な事情として評価される可能性があります。
(3)記録の重要性を理解しておく
会社側としては、次のような記録を丁寧に残しておくことが、結果的にトラブル予防につながります。
- 解任を検討し始めた経緯や理由のメモ
- 関係者と行った話し合いの内容(議事録やメモ)
- 役員本人に対して、どのような説明や注意をしてきたかの記録
これらは、後から「きちんとした理由とプロセスに基づき解任を行った」と説明するための土台になります。
感情的対立から「取締役 解任 クビ」に踏み切るリスク
役員解任は、本来「会社の将来のために経営体制をどうするべきか」という観点から検討されるべきものです。
しかし現実には、感情的な対立や人間関係のもつれが背景にあるケースも少なくありません。
(1)個人的な対立をそのまま解任の理由にしてしまう危険
例えば、社長と特定の取締役との関係が悪化したり社内で影響力を持つ人物と意見が合わないといった場合、感情的な流れのまま「取締役 解任 クビ」という方向に走ってしまうことがあります。
しかし、個人的な対立だけを理由にした解任は、法律上の「正当な理由」としては弱く、不当解任として争われるリスクが高くなります。
(2)社内の分裂・モチベーション低下のリスク
特定の役員を感情的に解任したように見える場合、次のような影響も出るおそれがあります。
- 他の役員や幹部が「自分もいつ同じ扱いを受けるか分からない」と不安を感じる
- 会社の意思決定が一部の人の感情によって左右されているように見える
- 社員からの信頼が低下し、モチベーションが下がる
結果として、短期的には対立が解消したように見えても、中長期的には会社全体のパフォーマンスに悪影響を与える可能性があります。
(3)外部から「お家騒動」と見られるリスク
役員解任が社外にも伝わると、取引先/金融機関/投資家などから、「会社内部で深刻な対立が起きているのではないか」「経営が不安定なのではないか」と受け止められることがあります。
このようなイメージが広がると、
- 新規の取引・融資に慎重になられる
- 社外からの信頼回復に時間がかかる
といった形で、経営に直接の影響が出るおそれもあります。
トラブルを避けるための役員解任の方法
最後に、会社側が役員解任を検討する際に、トラブルをできるだけ避けるための基本的な考え方を整理します。
(1)解任以外の選択肢も含めて検討する
役員の交代を考える場面でも、「解任」だけが唯一の方法とは限りません。例えば、
- 任期満了まで待つ(再任しない)
- 役職を変更して、別の役割を担ってもらう
- 双方が納得できる条件での辞任・合意退任を模索する
といった選択肢も考えられます。
もちろん、状況によっては早期の交代が必要な場合もありますが、「すぐに解任ありき」で進めると、かえってトラブルを招くリスクが高まります。
(2)解任を選ぶ場合の基本的なポイント
最終的に解任を選ぶ場合でも、次のようなポイントを押さえることが大切です。
- 解任の理由を具体的に整理しておく
- これまでの注意や改善要求の経緯を振り返る
- 話し合いの機会を設け、本人の意見も聞く
- 決定プロセスや内容を丁寧に記録として残す
こうした対応をとることで、後から「突然一方的に解任された」と受け止められるリスクを減らすことができます。
(3)解任通知書や説明の場を丁寧に設ける
解任を伝える場面では、「どのように」「どの言葉で」伝えるかも重要です。
- 事実と評価を分けて説明する
- 解任理由を、可能な範囲で具体的に伝える
- 相手の今後のキャリアや生活への配慮を示す
といった点を心がけることが、不要な対立や感情的な対決を避けるうえで役に立ちます。
また、可能であれば、
- 解任通知書など、書面でも内容を確認できるようにする
- 相手が内容に疑問を持った場合に相談できる窓口を示す
といった配慮も検討すべきです。
会社側が適切な理由と手続きに基づいて役員解任を行おうと努めることは、結果として、役員側・株主側・従業員側など、すべての関係者にとって「納得感のある形」で経営体制を整えることにつながります。
よくある質問(Q&A)
ここでは、「役員 解任」「取締役 解任」で検索される方から、よく寄せられる疑問をQ&A形式でまとめます。
第1章〜第7章の内容を、ピンポイントで振り返るイメージで読んでいただければと思います。
Q. 役員の解任はできますか?どのような場合に可能ですか?
- 会社法上、取締役は株主総会の決議によって「いつでも解任することができます」が、正当な理由のない任期途中の解任には損害賠償の問題が生じ得ます。
会社法上、取締役などの役員は、原則として株主総会の普通決議によっていつでも解任することができるとされています。これは、会社の経営を適切に行うために、株主が経営陣の人選を状況に応じて柔軟に見直せるようにするためのルールです。
一方で、任期途中で解任される役員の側から見ると、
- 残りの任期分の役員報酬を得られなくなる
- 役員退職慰労金(役員退職金)にも影響が出る
など、大きな不利益となります。
そのため、正当な理由がないのに任期途中で解任した場合には、会社がその役員に対して損害賠償責任を負う可能性があります。株主総会で解任すること自体は法律上認められていますが、解任の理由や手続きの内容によっては、会社側が金銭的な責任を問われ得る、というイメージを持っていただくと理解しやすいと思います。
Q. 役員を外す方法はありますか?(解任以外の選択肢)
- あります。任期満了による退任、役職変更、合意による辞任・退任などが考えられます。状況によって、どの方法が適切かは変わります。
役員を「外す」方法は、必ずしも解任だけではありません。例えば、次のような選択肢があります。
- 任期満了による退任
任期が来るまでは役員を続けてもらい、その後は再任しない方法です。
解任ほど対立が先鋭化しにくい一方で、時間はかかります。 - 役職・担当業務の見直し
代表取締役から平取締役に変更する、担当領域を変えるなど、役員のまま役割を調整する方法です。 - 話し合いに基づく辞任・合意退任
役員本人とも協議し、一定の条件(退職慰労金や今後の説明の仕方など)を整えたうえで辞任・退任という形を取る方法です。
会社側としては、「本当に解任が必要なのか」「他の方法では対応が難しいのか」を慎重に検討することが大切ですし、役員側としても、「どの選択肢が自分にとっても現実的か」を冷静に考える必要があります。
Q. 解任と退任・辞任の違いは何ですか?
- 簡単にいうと、「任期どおりに終えるか」「途中で会社の判断で外されるか」「本人の意思で辞めるか」の違いです。
- 退任
任期満了など、あらかじめ予定されていた理由で役員の任期が終わり、その結果役員でなくなることをいいます。
予定どおり任期を終えた形になるため、残りの任期分の報酬を失うという問題は生じにくいです。 - 解任
任期の途中で、会社の判断により役員の地位を失わせることです。
本来の任期が残っているにもかかわらず役員から外されるため、正当な理由がない場合には損害賠償が問題になります。 - 辞任
役員本人の意思で役員を辞めることです。
辞任届を提出して受理される場合が典型的です。
注意が必要なのは、実際には会社から強い圧力を受けて退くことになったにもかかわらず、形式上は「辞任」「円満退任」とされているケースです。
このような場合、「本当に自分の自由な意思による辞任といえるのか」「実質的には解任と同じではないか」を慎重に検討する余地があります。
Q. 役員解任で退職慰労金(役員退職金)は必ずもらえますか?
- 「必ずもらえる」とまではいえません。会社の規程や決議の内容、解任の理由によって、支給の有無や金額が争点になることがあります。
退職慰労金(役員退職金)は、
- 定款
- 株主総会決議
- 取締役会決議
などにより、その有無や金額の決め方が定められていることが多いです。
一般的には、在任期間や会社への貢献度を踏まえて支給されますが、
- 不祥事や重大な義務違反があると主張されている場合
- 「解任だから退職慰労金(役員退職金)は出せない」という説明がされている場合
などには、会社が退職慰労金(役員退職金)の減額や不支給を主張してくることもあります。
もっとも、会社が「不支給」と言っているからといって、必ずしもそれが妥当とは限りません。
- 本当に重大な不祥事といえるのか
- 退職慰労金を全額カットするほどの事情があるのか
- 規程や過去の支給実績とのバランスはどうか
といった点を踏まえて、
退職慰労金の扱いが適切かどうかを検討する余地があるケースも多くあります。
退職慰労金の問題は、将来の生活に直結する重要な部分ですので、会社の説明に疑問がある場合には、一度専門家に内容を見てもらうことをおすすめします。
取締役・役員解任で悩んだらご相談ください
取締役・役員は法律上「いつでも解任できる」一方で、正当な理由のない任期途中の解任については、会社に損害賠償責任が生じる可能性があります。形式上の「退任」「辞任」でも、実質は解任に近い扱いとなっているケースも少なくありません。
「おかしいかもしれない」と感じたら、
- 解任に至る経緯・理由・やり取りをメモと資料で整理する
- 辞任届や合意書に安易にサインしない
- 早めに専門の弁護士へ相談する
の3点を意識していただくことが重要です。
取締役・役員の解任トラブルは、会社法だけでなく、退職慰労金や株式、今後のキャリアなどが絡む、複雑で精神的負担も大きい問題です。
弁護士法人M&A総合法律事務所は、会社から不当解任・強制的な辞任の扱いを受けた役員側の支援に力を入れており、解任理由や手続きの妥当性、損害賠償・退職慰労金の可能性などを整理しながら、会社との交渉方針を一緒に検討します。
早い段階で相談することで、残すべき証拠や避けるべき対応が分かり、不利な条件での「泣き寝入り」を防ぎやすくなります。
——————
本記事で紹介している内容は、執筆時点の法令や通達等を前提とした一般的な情報提供であり、個別の事件についての法的助言や税務アドバイスではありません。実際に非上場株式の譲渡を検討する際には、必ず最新の法令や税制、具体的な事情を踏まえて、弁護士や税理士などの専門家に相談したうえで判断してください。
お困りではありませんか?