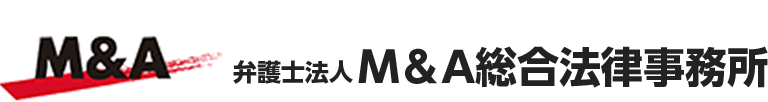代表取締役の解任(解職)とは?社長解任クーデターで使用される!解任することができるケースや、手続きと流れを解説

代表取締役の解職とは、代表権を失い平取締役になることです。法律上は「解職」が正しく、「解任」と意味合いは異なります。
「解任」とは、取締役を辞めさせることです。そのため、代表権を失うだけでなく、取締役の地位も喪失し、会社も辞めなければなりません。
代表取締役の解職は、「社長解任クーデター」で使用される方法であり、社長解任クーデターで解任が使用されることはほとんどありません。
今回は、代表取締役の解任・解職の違いやメリット・デメリット、手続きの流れを解説します。
代表取締役の解任・解職とは?
代表取締役の解職とは、会社の意向で代表取締役が平取締役になることです。代表権は失われますが、取締役の地位は残ります。解職の手続きは、通常、取締役会や株主総会で行われます。
代表取締役が解職される理由は、義務の怠慢や会社に経済的な損失を与えたとか、違法行為をおこなったとかさまざまです。代表取締役解職後は、新たな代表取締役を選任する必要があります。
代表取締役の解職と取締役の解任との違い
代表取締役の解職と取締役の解任は、言葉が似ていますが、意味合いは異なります。
代表取締役の解職
先述したように、代表取締役の解職とは、会社の意向で代表取締役が平取締役になることです。
代表取締役の解職には、株主総会の手続きは必要ありません。取締役会を開催することにより行えるため、容易かつ素早い対応が可能です。ですので、「社長解任クーデター」のためには、代表取締役の解職の手法が使用されます。ただし、代表取締役を解職されても平取締役の地位は残ります。
代表取締役の「解任」と言われることもありますが、正しい表現は「解職」です。
取締役の解任
取締役の解任とは、会社の意向で取締役を辞めさせることです。代表取締役が解任されると、代表権のみならず取締役の地位も失います。
「解職」と「解任」は区別されずに使用されることもありますが、意味合いが異なります。
取締役の「退任」と「辞任」との違い
役員がその地位を退く方法には、「解職」や「解任」の他に、「退任」と「辞任」があります。これらも混同されがちですが、意味合いが大きく異なります。
退任とは、取締役が任期満了により、自動的にその地位を終えることを指します。法律で定められた任期(原則2年、非公開会社は最長10年など)が到来すれば、特別な手続きなしに役目を終えます。会社側や取締役自身の意思とは関係なく、時期が来れば自然に役目を終える形です。
一方、辞任とは、取締役が自らの意思で、任期途中にその地位を退くことを指します。辞任届の提出など、取締役自身の明確な意思表示によって行われます。会社が強制する「解職」や「解任」とは異なり、取締役本人の自由な意思に基づくものです。
「解職」や「解任」は会社が強制的に役員を辞めさせる手段であるのに対し、「退任」と「辞任」は役員の任期終了や自身の意思によるもので、これらは会社が損害賠償請求を受けるリスクが低い方法となります。
代表取締役を解任・解職できるケース
取締役を解任する「正当な理由」は、主に以下のとおりです。
- 健康悪化による職務の執行に支障があるケース
- 法令や定款に違反する不正行為を行うケース
- 職務の能力が不適任だったケース
これらのように正当な理由がある場合、取締役は解任によって生じた損害賠償を請求できません。
他方、代表取締役の解職は、取締役会等が経営判断として任意に行うことができ、正当な理由は求められていません。ここからも、「社長解任クーデター」のためには、代表取締役の解職の手法が使用されます。ただ、あまりにも正当性に欠ける場合は、代表取締役の解職であっても、損害賠償請求をされる可能性はあります。
「正当な理由」の具体的な判断基準と例
「正当な理由」の有無は、解任後の損害賠償請求の可否に直結する非常に重要な要素です。判断は非常に専門的で個別性が高いため、弁護士など専門家のアドバイスが不可欠です。
「正当な理由」が認められやすい具体的な状況としては、
- 著しい経営能力の欠如(明らかに期待される事業遂行能力に欠け、会社に具体的な損害を与えている、または与える可能性が高い場合)
- 重大な法令・定款違反(会社法や会社の定款に違反する行為が確認され、会社の信用や運営に悪影響を及ぼしている場合)
- 会社に対する背信行為(会社資産の私的流用、秘密情報の漏洩、競業避止義務違反など、会社への忠実義務に反する行為)
- 職務の継続的な不履行(健康上の理由など、正当な理由なく長期にわたり職務を遂行できない状態が続く場合)などが挙げられます。
反対に「正当な理由」が認められにくい具体的な状況としては、
- 単なる意見の相違(経営方針や戦略に関する他の役員との意見の食い違いのみでは、一般的に正当な理由とは認められません)
- 軽微な判断ミス(経営判断に伴う単純なミスや、会社に重大な影響を与えない程度の失敗)
- 経営者の都合や感情(個人的な好き嫌いや、明確な理由なく「なんとなく合わない」といった理由での解任)
などが考えられます。
代表取締役を解職するときの手続きの流れ
ここからは、代表取締役を解職するときの手続きの流れを解説します。
取締役会設置会社と取締役会非設置会社で流れが異なるため、それぞれ分けて解説します。
取締役会設置会社の場合
取締役会設置会社の場合の手続きの流れは、主に以下のとおりです。
- 取締役会の招集
- 解職決定の投票
- 取締役会議事録の作成
- 事務手続きの変更
取締役会の招集
取締役会設置会社の場合は、まず取締役会の招集を行います。
どの取締役でも招集手続きを行えますが、会社によっては招集手続きを行う取締役が決まっていることも多いようです。
招集通知を取締役全員に送れば招集は完了です。招集通知は取締役会を開催する日の1週間前までに発送してください。
解職決定の投票
取締役会で解職を決定するために解職決定の投票を行います。議決に参加できる取締役のうち過半数の賛成があれば、代表取締役は解職されます。
解職によって代表取締役がいなくなってしまったときは、新たな代表取締役を決める選定決議を行います。
代表取締役が2人いて、1人が解職されたときは選定決議を行う必要はありません。
取締役会議事録の作成
代表取締役の解職後は、取締役会議事録を作成します。新たに代表取締役の選定決議を行った場合は、選定決議についても取締役会議事録を作成しましょう。
事務手続きの変更
代表取締役の解職により、事務手続きの変更が必要です。
登記簿への変更申請や税務申告など法的な文書や登記情報を変更しましょう。登記手続きについて詳しくは後述します。
取締役会非設置会社の場合
取締役会非設置会社の場合は、代表取締役を選んだ方法によって解職の方法が異なります。
- 代表取締役を定款で定めている場合
- 代表取締役を互選で選んだ場合
- 株主総会で代表取締役を選んだ場合
代表取締役を定款で定めている場合
定款によって代表取締役を選んでいる場合、条項に名前が記載されています。そのため、定款から条項を削除しなければなりません。
定款変更の手続きを行えば、条項を削除できます。手続きを行うためには、株主総会で特別決議を行う必要があります。特別決議には2/3以上の賛成が必要です。
定款変更の手続きを行うときは、取締役の解任になるため、取締役も辞めなければなりません。また、株主総会後には、株主総会議事録の作成も必要です。
代表取締役を互選で選んだ場合
代表取締役を互選で選んだ場合は、取締役の過半数が賛成すれば代表取締役を解職できます。
株主総会で代表取締役を選んだ場合
株主総会で代表取締役を選んだ場合は、株主総会で決議を行います。成立させるには、株主の過半数の賛成が必要です。
この場合も取締役の解任になるため、取締役の地位も失います。
取締役の解任をするときの手続きの流れ
取締役の解任をするときの手続きの流れは主に以下のとおりです。
- 取締役会の招集
- 株主総会の招集
- 株主総会での解任決議
- 取締役解任の登記
取締役会の招集
まず、取締役会の招集を行います。
取締役の解任決議を行うときは、株主総会を開催しなければなりません。そのため、取締役会設置会社では、取締役会の招集が必要です。
招集通知を取締役全員に送れば、招集は完了です。解任したい取締役に対しても招集通知を送らなければなりません。
取締役会が開催すれば、株主総会の招集決議を行います。出席した取締役の過半数が賛成すれば取締役会決議は成立です。
株主総会の招集
株主に株主総会の招集通知を送り、株主総会の招集を行います。
株主総会の開催日は、株主総会の招集通知の発送日から期間を空ける必要があります。公開会社は14日以上、非公開会社の場合は7日以上必要です。
株主総会での解任決議
株主総会での解任決議は、議決権の過半数を保有する株主のうち、株主の議決権の過半数の賛成があれば成立します。
また、取締役の解任が否決された場合に、一定の株主は裁判所に解任の訴えを提起し、取締役を解任できるケースもあります。詳しくは後述します。
取締役解任の登記
取締役の解任決議が成立したら、 取締役解任の登記が必要です。登記は、取締役の解任日の翌日から2週間以内に行わなければなりません。
登記を行えば、取締役の解任の手続きは完了です。
取締役解任登記を怠った場合のリスク
取締役の解任は法的に完了しても、登記を怠ると会社に大きなリスクが生じます。
まず、解任の効力が第三者に対抗できません。登記は、会社に関する重要な事実を社会に公示する役割があります。解任の登記がされていない場合、解任されたはずの取締役がまだ取締役であると信じて取引を行った第三者に対して、会社が「もう取締役ではない」と主張できなくなる可能性があります。
さらに、会社が変更登記を怠ると、会社の代表者に対し、100万円以下の過料という行政罰が課される可能性があります。
取締役の解任の訴えとは
先述したように、取締役の解任は否決される可能性もあります。その場合、一定の株主は取締役の解任を求める訴えを提起できます。(会社法854条)
解任の訴えを行えるのは、「総株式の議決権の3/100」か「発行済株式の3/10」以上の株式を6ヶ月前から保有している株主のみです。解任の訴えを行い、裁判で認められれば取締役を解任できます。
代表取締役を解任・解職するときに必要な準備
代表取締役を解任・解職するときに必要な準備は、主に以下の3つです。
- 取締役や株主の賛成
- 法的手続きの準備
- 新たな代表取締役の選定
取締役や株主の賛成
代表取締役の解職には、解職であれば取締役会の過半数以上の賛成が必要です。そのため、事前に信頼を築き、賛成派を増やす必要があります。解任であっても、株主総会を開催するためには取締役会の承認が必要ですので同様ですが、さらに株主の過半数以上の賛成が必要ですので、株主との間においても、事前に信頼を築き、賛成派を増やす必要があります。
代表取締役に気づかれないようにしなければならないため、どの取締役や株主から賛成を得るかなど検討した上で行動すべきです。
法的手続きの準備
代表取締役の解職には、必要な書類などの準備が必要です。
取締役会の開催や書類の作成など代表取締役の解職の流れを確認しておきましょう。
新たな代表取締役の選定
代表取締役が1人の会社の場合、新たに代表取締役を決める必要があります。代表取締役の解職後、スムーズに経営を進めて行くためにも、新たな代表取締役候補を決めておかなければなりません。
また、事前に新たな代表取締役に説明しておくことも重要です。
代表取締役の解職と取締役の解任の選び方
ここからは、代表取締役の解職と取締役の解任の選び方について解説します。
2つの手続きには、メリットやデメリットがあるため、適切な方法を選びましょう。
代表取締役の解職のメリット
代表取締役の解職のメリットは、株主総会を開催する必要がなく、手続きをスピーディに行えることです。
そのため、代表取締役としての責務を果たせず、会社に損害が出ている場合は、すぐにでも代表取締役から代表権を取り上げなければなりません。このようなときに、株主総会は必要なく行える代表取締役の解職は有効です。
代表取締役を解職することで、組織の改善や取締役会の活性化・企業のイメージ回復などさまざまなメリットがあります。
代表取締役の解職のデメリット
代表取締役の解職のデメリットは、その代表取締役に平取締役の地位が残ることです。
代表取締役は代表権は失っても平取締役として会社には残っているため、会社から辞めさせることはできません。そのため、場合によっては会社に悪影響を及ぼす可能性もあるため、注意が必要です。
また、代表取締役の解職は、ほか他の取締役への根回しをしておく必要があります。事前に根回しをしておくことで、解職を反対されるリスクを抑えられますが、代表取締役に感づかれ、返り討ちにあってしまう可能性も生じます。
取締役の解任のメリット
取締役の解任のメリットは、代表取締役だけでなく、取締役も辞めさせられることです。そのため、一度の手続きで代表取締役と取締役の地位を取り上げることができます。
代表権を剝奪するだけでなく、取締役の地位も喪失させることができるため、代表取締役を完全に会社から辞めさせたいときに有効な方法です。
取締役の解任は、企業の健全性を確保したり、コーポレートガバナンスを強化したりするメリットがあります。
取締役の解任のデメリット
取締役の解任のデメリットは、株主総会が必要になるため、株主への根回しをしておかなければ否決される可能性があることです。株主総会を開催するために、招集通知を送付する必要もあり、手間や時間もかかります。
また、株主総会を開催するためには、取締役会において株主総会開催手続きを行う必要があるため、取締役への根回しも必要ですし、取締役会において株主総会開催手続きを行う時点で、代表取締役が知るところになってしまいます。
また、取締役の解任は、正当な理由がなければ、損害賠償を請求されるリスクもあります。
代表取締役の解任・解職するときのリスク
代表取締役の解任・解職するときのリスクは、主に以下の3つです。
- 法的リスク
- 組織内の不安定性
- 取引関係の損失
法的リスク
代表取締役を解任・解職するときは、対象の代表取締役に解職の有効性について訴訟を提起される可能性もあり、会社や取締役に対して、損害賠償請求される可能性があります。
適切な方法で解任・解職を行うため、専門家にアドバイスを受けた上での行動が必要です。
組織内の不安定性
代表取締役の解任・解職を行うことで、組織内には大きな変化が起こります。それにより、会社の従業員や株主・取引先などから信頼を失う可能性があります。
組織内の不安定性を防ぐためにも、代表取締役の解任・解職をするときは、信頼を失わないような対策を考えてください。
取引関係の損失
代表取締役は、企業の取引を行っていることが多く、取引関係を把握されるリスクがあります。また、新たな代表取締役が信頼関係を築くまでに、取引関係の中止や再交渉になる可能性もあります。
取引関係の損失を防ぐためにも、慎重な関係構築が必要です。
代表取締役の解任・解職後の登記手続きについて
代表取締役を解任・解職後は効力発生日から2週間以内に登記手続きを行わなければなりません。
登記申請に必要な書類は、取締役会設置会社と取締役会非設置会社で異なります。
取締役会設置会社に必要な書類は以下のとおりです。
- 取締役会議事録
- 就任承諾書
- 新代表取締役の印鑑証明書
取締役会非設置会社に必要な書類は以下のとおりです。
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 新代表取締役の就任承諾書
- 新代表取締役の印鑑証明書
取締役会非設置会社の場合は、互選によって解職した場合は、別に「取締役の決定書」や「定款」が必要になるため、解職した方法によって異なります。
代表取締役の解職の事例
代表取締役の解職の事例を2つ紹介します。
- アルビス代表取締役地位確認請求事件
- 積水ハウス前会長解任劇
アルビス代表取締役地位確認請求事件
アルビス代表取締役地位確認請求事件は、会社の代表取締役が取締役会で解職され、新たに代表取締役に選定されたところに代表取締役の地位確認、決議の無効確認を求めて損害賠償を請求した事案です。
本件の主な争点は、解職決議の有効性や損害賠償請求権の有無です。判決の結果、解職決議は有効で、損害賠償請求は認められないとされました。
積水ハウスの会長交代
積水ハウスは、2018年に土地取引詐欺事件の社内対立によって会長が交代しています。前会長は、取締役会で解任されました。
これに対して前会長は、「詐欺事件の責任を明確化すべきだ」と解任動機を提案しましたが、否決されています。ガバナンスに問題があったとされており、新しいガバナンス体制を構築する取り組みがされました。
取締役の解任の事例
取締役の解任の事例を2つ紹介します。
- 会社に対する架空請求を理由とする 取締役解任事例
- 特定の業者と癒着して不当な利益を図った行為を理由とする解任事例
会社に対する架空請求を理由とする 取締役解任事例
製造業の会社で、取締役が会社に対して架空の請求を行い、自分自身にそのお金を環流させていたことにより、取締役の解任が行われました。
裁判の結果、取締役の解任には正当な理由があったとされ、損害賠償請求は認められませんでした。
特定の業者と癒着して不当な利益を図った行為を理由とする解任事例
代表取締役の解職・解任をされた理由は以下の2つです。
- 会社が管理する予定だった駅ビルのテナント候補会社の取締役に就任し、ほかの役員などに隠して出店の申込をした
- ほかの駅ビルの開発事業に関して、取締役会に相談せず設計請負契約を締結し、多額のリベートを関係者に取得させた
裁判の結果、正当な理由があったとされ、代表取締役の解職・解任は認められました。
まとめ
今回は、代表取締役の解任・解職の違いやメリット・デメリット、手続きの流れを解説しました。
代表取締役の解職のメリットは、手続きを取締役会だけでスピーディに行えることです。しかし、取締役の地位は残るため、取締役も辞めさせたい場合は、取締役の解任を選びましょう。
また、取締役会設置会社と取締役会非設置会社によって手続きの流れも異なります。この記事を参考にして、自社の状況に合わせて手続きを進められるようにしてください。