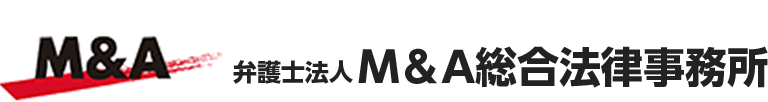役員の任期変更による強制退任の場合も残存任期役員報酬損害賠償請求をすることができます!

会社の取締役は、在任期間中に正当な理由なく役員の任期変更による強制退任をされた場合、会社法に基づいて残りの任期分の役員報酬を損害として請求することが認められています。
一方で、自主的な辞任とみなされる形で辞任届の提出を強要された場合、形式上は「辞任」であるため、会社法上の解任とは扱われず、残存任期分の報酬請求が難しくなると考えられます。しかし、実態として本人の意思に反して辞任させられた場合、その状況は実質的に「解任」と変わらないのではないかという疑問が生じます。
そこで今回は、「定款で役員の任期を短縮する変更して、役員を想定外に早期に退任させられた」において、残りの任期に対応する役員報酬を損害として請求できるのか詳しく解説していきます。
会社が役員の任期変更を行い否応なく強制退任になってしまった
取締役などを解任すると、解任取締役から残存任期の役員報酬の損害賠償を請求されるリスクがあります。会社側としては、損害賠償請求による金銭的な痛手や風評を回避したいという気持ちがあることでしょう。そのため、取締役を解任するときに損害賠償が発生しない方法を模索し、ずるい方法を使おうとすることがあるのです。
会社側が損害賠償請求リスクの回避方法として使う手段に、「取締役などの役員任期を変更し、退任させる」という方法があります。
役員の任期を定款変更により元の任期より早期に変更し、「任期が早くなった。だから、あなた(役員)も早期に退任していただきたい」と迫るわけです。会社は、早期に変更した任期通りに退任するわけだから、損害賠償請求は行えないだろうと考えるからになります。
役員任期変更強制退任の場合も残存任期役員報酬損害賠償請求は可能か?
このようなずるい手段を使われた場合、役員は表面上任期通りの退任です。そのため、損害賠償請求は難しいだろうと判断しがちです。決してそのようなことはありません。役員の任期早期変更強制退任の場合も、会社に対して賠償請求が可能なのです。
- 会社役員解任の法的ルールについて(役員を解任できるケース)
- 役員任期早期変更による役員の強制退任とは
- 役員の任期早期変更による強制退任で実際に賠償が命じられた判例
以上の3つのポイントを「役員の任期早期変更強制退任の損害賠償」を主軸にM&A弁護士が説明します。
役員を解任できるケースとは?会社役員解任の法的ルール
会社の取締役などの役員は、いわば会社の頭脳です。役員は会社を引っ張って行く存在だからこそ、解任や退任については通常の従業員とは異なる定めがあります。
会社役員解任については、会社法339条に基本的なルールが定められています。
| 会社法第339条
1 役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。 2 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。 |
会社役員解任ルール①・・・役員は株主総会で解任できる
会社の取締役などの役員は、株主総会で解任が可能です。
会社の役員には、基本的に任期が設定されています。しかし、任期満了まで役員の地位が絶対的に保障されるわけではありません。「任期満了まで解任できない」と定めてしまうと、役員の横暴により会社が傾いてしまう可能性や、解任されないからと報酬だけもらって仕事をしない可能性などが考えられます。
会社のために、役員は株主総会で柔軟に解任できるというルールを、会社法は設けているのです。
会社役員解任ルール②・・・解任された役員は残存任期役員報酬損害賠償請求できる
会社法339条にもありますが、解任された役員は「解任の正当な理由がある場合を除いて損害賠償が可能」です。
賠償請求の対象となる損害には、月額報酬に加え、過去の実績に基づく賞与、退職慰労金、役員社宅の供与等の経済的利益、また業績連動報酬やストックオプションが含まれる可能性もあります。契約書や社内規程に明記されていない場合でも、過去の支給実績等から認定されることもあります。
解任された役員には、任期まで務めるという約束がありました。任期まで役員を務めていれば、その分の報酬も発生したはずです。株主総会で任期満了前に解任されるということは、不測に職を失うということであり、収入が途絶えるということです。
会社役員側に解任される正当な理由があれば別ですが、役員として誠心誠意、会社のために尽くしていたのに解任されるということは、非情にも等しいことではないでしょうか。そのため、解任された会社役員に非がなかった(解任の正当な理由がなかった)場合は、解任された役員が会社に対して損害賠償請求できるのが会社法上のルールです。
株主総会で柔軟に解任できる。その代わり、役員に対して損害賠償の責任を負う。このように、法律でバランスを取っているのです。
請求できる損害賠償の額は、「役員が任期満了まで役員を務めた場合に受け取ることができた役員報酬の総額」です。解任時の役員報酬(月額)に解任から任期満了までの期間を乗じて算出するのが基本になっています。
月額の役員報酬が50万円で、任期満了まで残り半年の時点で解任された。この場合は、単純計算で300万円の損害賠償額になります。
会社役員解任ルール③・・・会社役員解任の正当な理由とは
ここまでの話を整理しましょう。
正当な理由としては、業務上の背任行為、経営判断の重大なミス、不正会計、社内外での信用失墜行為、心身の著しい不調などが挙げられます。裁判例では、これらの事実が合理的な証拠に基づいて主張されることが重要とされています。
- 取締役などの会社役員は株主総会で解任できる
- 解任に際して正当な理由がない場合は、解任された役員は会社に対して損害賠償請求できる
以上の2つのルールを踏まえ、では「正当理由とはどのような理由か」が問題になります。正当理由があれば、会社役員を解任しても損害賠償請求を免れる。正当な理由がなければ、会社は損害賠償の支払いという金銭的な痛手を受ける。会社としては「損害賠償の支払いなどしたくない」が本音でしょう。
解任の正当理由とは、どのようなものなのでしょうか。どのような理由があれば、会社は役員解任による損害賠償請求を免れるのでしょう。代表的な正当理由は次の2つです。
- 役員の不正な行為や法律違反が理由で解任した
- 役員の能力不足・経営へ失敗・株主と会社経営の方針が異なっていた
要するに、会社役員の経営ミスや法律違反、不正行為など、会社や株主に対して明らかに「やってはいけないこと」があった場合です。
ただ、経営上のミスを役員が犯したとしても、そのミスがただちに正当理由だと判断されるわけではありません。役員の能力不足も正当理由のひとつになり得ますが、どの程度が能力不足に該当するかは、判断がわかれるところです。正当理由がある解任に該当するかは、裁判所に打って出て、判決により決着をつけることも多くあります。最終的にはケースバーケースというところがあるのです。
ここで注目したいのは、役員解任の正当理由に「会社や他役員の事情」や「会社や他役員に不都合だから」などの、会社側の私的な事情や思惑、権力争いなどが一切含まれていない点です。
会社で派閥争いがあり、特定の役員が邪魔になった。よって、解任してしまおう。会社の思惑と役員の思惑がずれてしまった。邪魔なので、解任しよう。新しい会社オーナーと旧役員のそりが合わない。したがって、旧役員を解任してしまおう。このような、会社やオーナー、他役員の思惑や事情は正当理由には含まれません。
会社や他役員、オーナーなどの思惑や事情によって役員を解任する場合は正当理由に該当しないため、解任された役員の損害賠償請求が許されます。すると、今度は会社やオーナーが困るのです。
会社やオーナーは、不都合な人間(役員)は切りたいが、賠償の支払いはしたくないという本音があるからに他なりません。損害賠償を支払わなくていいように、ずるい手を使うことがあるのです。
ずるい手とは、「役員任期早期変更による強制退任」のことになります。
役員任期の早期変更による役員の強制解任とは?!
役員を任期中に株主総会で解任した場合、正当な理由がなければ、解任した役員から損害賠償を請求されてしまう。会社やオーナー、他役員の思惑によって解任する場合、解任による損害賠償請求が大きな問題になります。
解任された側の役員も事情を理解しているケースがほとんどなので、解任に納得していないことでしょう。解任された役員は、積極的に損害賠償を請求するケースが多くなっています。
会社側は、解任による損害賠償の請求を回避したいため「解任でき」なおかつ「損害賠償が発生しない」手段を用いようとします。それが、役員任期早期変更による役員の強制退任という手段です。
たとえば、会社オーナーが古株のA役員を解任しようと思っていました。A役員は、旧オーナー時代からの重鎮であり、社内でも信頼の厚い人物です。現オーナーにとっては目障りな存在でした。
そんなA役員を解任したいと考えているのですが、株主総会で解任すると損害賠償リスクがあります。何とか損害賠償リスクを回避したい。そんな思いで、オーナーは一計を案じました。A役員の任期を短くしてしまえばいいのです。
A役員の任期は10年。まだまだ任期が残っています。しかし、この任期を1年へと早期変更したらどうでしょう。10年の任期を満了するまでは、時間がかかる。A役員を会社から追い出すためには、まだまだ長い時を要します。時間がかかるからといって株主総会で解任すると、今度は損害賠償リスクが高い。それならA役員の任期を短くし、すぐに任期満了で役員を辞するように変更してしまえばいいわけです。
任期満了なので、株主総会で解任するようなリスクもありません。会社やオーナーにとっては上手い方法ですが、強制解任されるに等しいA役員にとっては、許しがたい方法ではないでしょうか。
一見、会社やオーナーにとってメリットしかない方法に思えます。しかしこの方法は完全なる悪手。なぜなら、任期早期変更による強制退任のケースでも、損害賠償請求が可能だからです。例のケースでは、任期早期変更によって半強制的に解任されるに等しい立場であるA役員が会社に対して損害賠償の請求ができます。
役員任期の早期変更による強制退任で実際に残存任期役員報酬損害賠償が命じられた判例
役員任期を実際の任期より早期へと変更し、株主総会によらず短縮した任期によって半強制的に退任させるということが過去に実際に行われ、裁判になったケースがあります。東京地裁、平成27年6月29日の判決です。
また、東京高裁平成19年7月25日判決では、定款上10年の任期を有していた取締役が、任期途中で不当に退任を強いられた事案で、残存任期全期間にわたる報酬全額が損害として認められました。任期の長短にかかわらず、任期短縮の合理性が争点となることがあります。
このように、東京高裁および東京地裁の判例は、いずれも定款変更により任期を短縮された取締役が退任に追い込まれた事案であり、取締役が定款変更により任期を短縮され、退任に追い込まれました。
任期満了による退任は、損害賠償請求できるケースには基本的に該当しません。しかし、不当に任期を短縮されて役員の地位を追われることは、ずるい手段に他ならないはずです。この方法が許されれば、多くの会社は損害賠償リスクを回避しながら役員切りを行うことでしょう。役員任期短縮により半強制的に退任へと追い込まれた役員は、会社法339条の類推適用で損害賠償を求めました。
東京地裁の平成27年6月29日の判決では、会社法339条の類推適用が認められ、任期早期変更で退任させられた場合は、損害賠償が認められるという結論が示されました。この判例のケースでは、解任の正当な理由があったという証拠もありませんでした。
この判例のケースでは、役員在任中に役員任期を早期変更されて半強制的に退任させられた場合にも、損害賠償請求が基本的に認められることを判示しており、役員が泣き寝入りする必要がないことを明確にしたとして有名です。
なお、この判例のケースでは、損害賠償の算定期間は退任した日の翌日から2年に限定されています。
役員の不当解任で損害賠償請求ができるケース
ここで、役員の不当解任で損害賠償請求ができるケースをまとめておきます。
任期途中で解任された取締役・監査役・会計参与・会計監査人などの役員が、以下のような事情に該当する場合には、会社に対して役員報酬相当額の損害賠償を請求できる可能性があります。
- 他の取締役や株主と経営方針が対立したことを理由に解任された
- 職務とは無関係な、私的な事情を理由に解任された
- 「もっと適任な人物がいる」という抽象的な理由で解任された
- 法令や定款に違反していないにもかかわらず、解任された
- 全く身に覚えのない理由で解任された
- 解任の理由が一切説明されないまま辞任を強要された
- 大株主による虚偽の主張や事実のねつ造によって解任された
会社法では、取締役や会計参与、監査役、会計監査人などの役員は、株主総会の決議によって、いつでも解任できると定められています(会社法第339条第1項)。この規定により、株主の多数決による形式的な決議があれば、法的には解任が成立します。
しかしながら、解任された役員が正当な理由もないままその地位を失うとなれば、それまで担ってきた役割や報酬への期待が一方的に損なわれることになります。そこで会社法第339条第2項は、解任された役員が「正当な理由がない」と主張できる場合に限り、会社に対して損害賠償を請求できる仕組みを設けています。
このように、会社法第339条第2項は、解任に正当な理由がない場合に役員の損害賠償請求を認めることで、解任された側の救済手段を確保しています。したがって、解任理由の妥当性を見極めることが、損害賠償請求の可否を判断するうえで極めて重要です。
損害賠償請求における時効期間について
会社法に基づく損害賠償請求に関して、判例や通説では、これは民法第709条に定められた不法行為責任ではなく、「法定責任」に分類されると解釈されています。そのため、時効の期間については5年間とするのが一般的な見解です。
一方、もしこれを不法行為に基づく損害賠償ととらえる立場であれば、消滅時効は3年とされることになります。
いずれにせよ、時効に関する見解の違いが争点になるリスクを避けるためにも、請求を長期間放置せず、できるだけ早い段階で訴訟の提起などの時効の中断措置を講じることが重要です。
損害賠償金に対する源泉徴収の要否について
従業員が不当解雇と判断され、その解雇が取り消された場合には、通常、解雇当時にさかのぼって雇用関係が復活し、その期間に対応する給与も支払われることになります。この際、雇用主は所定の所得税の源泉徴収を行う必要があります。
一方で、株式会社の役員については、会社法の規定により、株主総会の決議によっていつでも解任することが可能です。そのため、たとえ解任に正当な理由がなかったとして損害賠償の支払いが認められた場合でも、解任自体は有効であり、解任された取締役の地位が過去にさかのぼって回復することにはなりません。
役員の不当解任に対する損害賠償金は、役員としての業務に対する対価ではなく、正当な理由のない解任によって役員が受け取れなかった利益、すなわち「逸失利益」に対する補填に過ぎないと考えられます。
したがって、役員の不当解任に対する損害賠償金の支払いは役員報酬のような給与所得には該当せず、税法上は「一時所得」として取り扱われるべきものであり、会社側が源泉徴収を行う必要はないと解されます。
参照記事:国税庁「中途解任した役員に支払う会社法第339条第2項に基づく損害賠償金に対する源泉徴収の要否について」
最後に
定款で役員の任期を短縮する変更して、役員を想定外に早期に退任させることは、ほぼ解任と同じです。
とくにM&A(企業買収)後に、旧経営陣の排除を目的として任期を短縮するケースは、実務上しばしば問題になります。新オーナー側の一方的な判断で任期を切り詰める行為は、従来の地位を侵害する不当な措置として、損害賠償請求のリスクが非常に高いといえます。
役員任期早期変更によって予想外に早期退任させられてしまった場合は、前述したように、損害賠償請求が認められるという判例が存在します。株主総会での解任と同様に、損害賠償請求が認められるのです。
任期早期変更により強制退任では、泣き寝入りする必要はありません。
役員報酬の損害賠償請求権にも消滅時効があります。民法上、損害および加害者を知った時から3年、または退任時から5年で請求権が時効により消滅するおそれがあります。請求を検討している場合は、早期の法的対応が必要です。
会社による任期短縮や強制退任の過程において、名誉を著しく毀損された、人格権を侵害されたような場合には、民法上の不法行為責任に基づいて慰謝料請求が可能な場合もあります。
今まで会社を真摯な気持ちで支えてきたのです。任期を動かすことによってリスクを回避しつつ役員を切るなど、言語道断です。
判例や会社法の趣旨に照らしても、任期短縮を悪用して役員を退任させることは、法的にも許容されるべきではないといえます。心の平穏やけじめのためにも、しっかりと損害賠償請求を行うことをおすすめします。